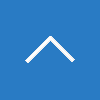ケルヒャース
ケルヒャース
チーム
クリーナーを
使おう

一時期のブームで、スチームクリーナーもずいぶんと認知されるようになった。
ホームセンターはもちろん、デパートやカー用品店でも手に入れることができる。
だが、「思ったほど汚れが落ちない」という意見も耳にする。
そんなあなたはスチームクリーナーの使い方、いや選び方が間違っていないだろうか?
世界ナンバーワンのシェアを誇るメーカー「ケルヒャー」製のクリーナーを例にとり、
上手な使い方を見てみよう。
※こちらの商品は販売終了いたしました。
記事内では、取材を行なった当時に販売されていた機種を使用しており、現在販売しているものとは仕様・操作方法等が異なります。
同等品等の案内は致しかねますので、ご理解のうえ、当情報のご利用をお願いいたします。
また掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が被った損害に対して、
弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。
基本の使い方はとても簡単
スチームクリーナーとは、高温の蒸気を勢いよく汚れに吹きつけながら落としていく、というもの。
普通の掃除機が汚れを「吸い取る」のに比べるとまるっきり違う。
さてその蒸気だが、これはスチームクリーナーの内部で作られる。しくみはこうだ。まず水をクリーナー本体のタンクに入れる。
その水を電気で沸騰させタンク内で高温のまま保温。そしてノズルの先から小出しに蒸気を出して汚れを落としていく。
では実際にスチームクリーナー「K1201プラス」を使って、じゅうたんにこぼしてしまったソースのシミを落としてみよう。

最初からこんなに豊富なパーツがついてくる
1
これが「K1201プラス」の本体と標準付属品。
ヘッドと一体になったホース、フロアーブラシ、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ(5コ)、延長パイプ、クロス、ハンドブラシ用カバーと、標準でついてくる付属品がとても豊富なのがうれしい。
さらにケルヒャーシリーズと言えば豊富なオプションパーツ。この「K1201プラス」にも、別売りのパーツを組み合わせて使うことができる。

水は1.6リットルまで入る
2
まず、キャップを開けて本体のボイラータンクに水を入れる。タンクは1.6リットルの容量があるから、ごく一般的なやかん一杯分がまるまる入る。
ケルヒャーのスチームクリーナーが一貫してこだわっているのが、『安全性』だ。スチームクリーナーという性格上、熱~い蒸気をたくさん使うわけなのでヤケド防止には気を使う。

電源スイッチはココ
そこで「K1201プラス」ではバルブの内部がピストンになっていて、中が高温(145℃)に達するとキャップが空回りして開かないようになっている。小さな子供が誤ってキャップを開けてしまい、熱い蒸気やお湯が吹き出る・・・という心配がない。
このほかにも「本体のON/OFFスイッチ」と「ノズル手元のロック」の2重ロックなど、ケルヒャーの安全にかける手間はなかなか立派である。

本体のランプが消えたら準備完了
3
水を入れてキャップを閉めたら、本体のスイッチを「ON」にする。
電気の力で水を沸騰させるまで約20分。
待っている間に、ここでちょっと蒸気に関するお話を。
「K1201プラス」は電源を入れている間、常に中のお湯を沸騰し続けている。お湯の沸騰といえば温度は100℃であるが、「K1201プラス」では圧力鍋と同様のしくみを利用して内部を145℃にキープしている。
それはなぜか?
スチームクリーナーでは中の温度が高いほど「質の良い蒸気」を生み出すことができる。質の良い蒸気=汚れを落とす能力のこと。つまり、蒸気が高温であるかどうかが、スチームクリーナーの性能を左右する。
145℃をキープした蒸気もノズルから出て外気に触れることで100℃になってしまうが、それでも温度が高いため効率よく汚れ落しができるというわけだ。
ちなみに、スチームクリーナー売場には「K1201プラス」のような大きなタンクをもつ「ボイラータイプ」のほかに、手軽な「ハンディタイプ」も並べられている。
ハンディ式は小柄なぶん、タンクの容量が小さく内部で高温を保つことができない。本体の中の熱した鉄板の上を、水が通過することで蒸気になるというしくみ で蒸気を出しているが、その時の温度は85℃くらいというから「ボイラー式」が性能で勝っていることがわかるだろう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
 |
 |
 |
| 加熱タイプ | ボイラー式 (中のタンクで常に沸騰している) |
パネル式 (熱した鉄板の上に水を通す) |
| 重量 | 5kg | 1.7kg |
| 噴出温度 | 約100℃ | 約85~90℃ |
| 手元でのスチーム操作 | できる | できない |
| 水タンク容量 | 1.6リットル | 0.5リットル |
| 連続作業 | 約30分 | 約10分 |
| タンクのキャップ | ある一定の温度まで下がらないと開けることができない「安全バルブ」設計。 お湯が吹き出る心配なし。 |
スイッチを切ると水タンクが取り外せ、 キャップも開く。 |
| 空焚き防止センサー | あり。 タンク内の水が減ってくると本体の空焚き防止用赤ランプが点灯し、警告。 自動的に加熱停止する空焚き防止センサーがついている。 |
なし |
| 操作性 | 本体は床に置くので、手元は軽い。 ホースが2mなので高いところの作業も楽。 |
一見コンパクトで手軽そうだが重い本体を常に持ち続けるのは大変。高く持ち上げると腕が痛い。 |
(ケルヒャージャパン作成資料による)
シミ汚れが落ちる瞬間を見た!

レバーを握ると蒸気が出る
スイッチを入れて待つことおよそ15分。本体のランプが消え、準備ができたようだ。早速「シミ落し」に使ってみよう。手元のノズルについたレバーを握ると、白い蒸気が勢い良く飛び出る。

スポットノズル(右)延長ノズル(左)
(別売りオプション)
今回は標準付属のノズルヘッドに別売りオプションの「スポットノズル」(先端の赤いパーツ)を取り付け、より狭い面積にピンポイントで蒸気を当てられるようにしている。

コーヒーがこぼれたシミ
カーペットに着いたシミは、コーヒーをこぼして1ヶ月経ったもの。青いカーペットの中でこげ茶色のシミがひときわ目立つ。
右手にノズル、左手にクロスを用意する。蒸気を真上から当てるのでなく、ななめ上または横側から当て、反対側に置いたクロスで蒸気を押さえながら受け止めるというやり方が上手な使い方だ。クロスは標準で1枚ついてくるが、これは家にある雑巾などで代用可能。

当て布を用意しよう
レバーを握って蒸気を当てる。ノズルの先端をシミに近づけ、蒸気で汚れを吹き飛ばす。白いスチームに手を近づけているから熱そうに見えるが、実際はさほどではない。「あたたかい」という表現がぴったりくるほどの温度だ。
シミが落ちたかなとクロスをめくってみると・・・・・・見事きれいにシミはカーペットから落ち、クロスに移っている。まるで魔法のようにシミが取れてしまった。

シミに直接蒸気を当てる
また、シミが取れたカーペットだが、蒸気を当て続けたというわりには思ったほど濡れていない。これは蒸気の温度が高温であるため。普段水を嫌うような、じゅうたんや畳などにも使やすいというわけだ。

みごとシミは落ち布に移った
なお、毛足の長いじゅうたんに蒸気を当てると縮んでしまう可能性もある。あらかじめ目立たないところで試してから行なうようにしたい。
床のじゅうたんや窓ガラスをすっきりきれい

フロアーノズル(標準装備)にはさみこむ
スチームクリーナーは、コーヒーをこぼしたシミのような部分的な汚れに有効なだけではない。床のじゅうたん全体に蒸気を当てることで、ベタつきをなくしてじゅうたんをふっくらとさせる効果もある。さらに、高温のスチームが中に入り込んだダニを死滅させることもできる。
床に使う場合は、まず掃除機をかけて大きなごみやホコリを取り除いておく。そのうえで写真のようにクロスを「フロアーノズル」に巻いて使う。フロアーノズ ルは両端が洗濯バサミのようなクリップ形状になっており、ここにクロスを挟み込むことができる(クロスは標準で1枚付属だが、家庭にある雑巾でも充分。タ オル生地のものが水をよく吸収するのでオススメ)。

掃除機と同じように使う
じゅうたんだけでなく、畳やフローリングの床の場合でも問題ない。同じようにクロスを巻いて使おう。
使い方のポイント
-
・ 床をクリーニングする際は、シミ取りの場合よりスチームの量を減らす。
(「K1201プラス」は手元でスチーム量の調節が可能。) -
・変質や変色を防ぐために1ヶ所にしつこく蒸気を当てすぎることは禁物。特にフローリングの場合は要注意。
(ワックスをはがしてしまう可能性がある。) - ・スチームによるクリーニングをした後は部屋を十分換気して、水分を完全に乾かそう。

ノズルをつけかえても蒸気は勢いよく出る
窓ガラスは内側も外側も汚れがついているもの。空気の中のホコリはもちろん、排気ガスや雨水、手アカまで、汚れの原因はさまざまだ。年末の大掃除ぐらいしか窓ガラスを掃除しなければ、その汚れが蓄積されてクリアな窓じゃなくなってしまう。
だが、実際に窓ガラスをきれいにするのは面倒なもの。洗剤とバケツを用意し、1枚拭いて雑巾を洗って・・・の繰り返しはなかなか大変な作業だ。
スチームクリーナーはここでも大活躍する。

窓についた汚れを浮かしてとる
窓には窓の、別売りオプション製品がある。その名も「窓用ノズル」。掃除機のヘッドに似た形状で、先端にゴム製のスクレイパー(水かき)がついているそれ は、パッと見たところ結露取りの製品のようにも見える。熱い蒸気で汚れを溶かし、スクレイパーでかき取るというしくみだ。

窓用ノズル(別売りオプション)

アミ戸にはハンドブラシが有効
使い方のポイント
- ・窓ガラスの下にクロスを敷いておく。床や周囲の壁紙を汚さないためだ。
- ・いきなり蒸気を当てずに、遠くから徐々に蒸気をガラスに近づける。その後でノズルをガラス面に押し当てて、ゆっくりスライドさせるように使う。
- ・針金入りのガラスの場合、高温で中の針金が膨張する場合がある。1ヶ所に集中して蒸気を当てすぎないように気を付けよう。特に冬は注意。

こんなに汚れていた!
窓周辺のアミ戸やサッシにも使える。アミ戸のクリーニングは、標準付属の「ハンドブラシ」にタオル地の専用カバーをつけて行なう。汚れで目詰まりしていたようなアミ戸も、スッキリきれいになることは間違いない。
(アミ戸は耐熱温度がさほど高くないので、スチームを1ヶ所に当てすぎないのがポイント。)

サッシの溝は延長ノズルで
最後にサッシのレール部分を掃除したい。窓ガラスについていた汚れが先ほどのスチームクリーニングで下のレール部分に落ちている。ノズルヘッドに「延長ノズル(別売り)」をセットし、こびりついたような汚れも吹き飛ばして落とすことができる。
毎日見ていながら、普段なかなか手を入れることができない窓ガラス。スチームクリーナーでクリアな視界を確保すれば、外の景色も違って見えるかもしれない。
汚れが垂れないエアコン掃除

エアコンの前カバーを開ける
最近増えているのがエアコン内部のスプレー洗浄剤。スプレーするだけでエアコン内部の汚れを落とし、除菌もできるというスグレモノだが、スチームクリーナーも蒸気の力で同様のことができる。
まずエアコン本体前面のカバーを開ける。フィルターが見えるが、これは熱に弱い材質のものなので取り外しておく。

フィルターもはずす
標準付属の延長パイプを継ぎ足し、高いところの作業をラクにできるのがポイントだ。右手にノズル、左手にクロスを持ってはね返りを防ぐように蒸気を本体に当てる。
蒸気の水分が足元に垂れてきそうだが、そこは心配ご無用。水はエアコン内部から外に置かれたドレンホースへ伝わるので、部屋の中に汚れた水が落ちてくることはない。
落ちてくるとしても水滴程度なので、クロスでサッと拭き取る程度。

内部の除菌もできて清潔
ところで、使っている「K1201プラス」は本体とノズルが離れているので、こういった高所の作業をする際はノズルだけを手に持てば良い。一方、ハンディ タイプでは水の入った本体ごと持ち上げる。小型の製品といえども重量は2kgほどとなり、かなり重たいものを上まで持ち上げる覚悟が必要だ。
ガスレンジの焦げを落とせる

ソースがこぼれて焦げついてしまった
キッチンのガスレンジは、料理のふきこぼれが焦げたりして汚れやすい。すぐに拭き取ればよいが、時間が経つにつれ落とすことは難しくなってくる。

蒸気を充分にあてて軽くこする
スチームクリーナーのノズルに別売りオプションの「真ちゅうブラシ」をつけ、レンジ台の焦げを軽くこすってみよう。高温の蒸気が焦げを溶かし、いとも簡単に取り去ってくれる。
(真ちゅう製のブラシなので多少キズがつく場合もある。)

ガス台まわりの焦げも落とせる

排水溝の黒ずみにも効果あり
蒸気は高温だから、排水口のヌメリ汚れや黒ずみもすっきり落としてくれる。漂白剤を使うよりも、手や環境にやさしいクリーニングができそうだ。
クルマのホイールにも有効

泥や油、ブレーキ粉で汚れたホイール
最後に紹介するのがクルマのホイール汚れを落とす例。クルマのホイールはブレーキパッドから出る粉塵や、アスファルト路面の油などで非常に汚れがつきやすい。
水や洗剤をかけただけの洗車ではこれらの汚れを落とすのは難しく、専用のクリーナー液を使ってブラシでゴシゴシこすらなければきれいにならない。もちろんこれは大変な労力。よほどホイールにこだわりのある人じゃないときれいに保つことは難しいのである。

真ちゅうブラシでこすって落とす
さて、写真のように汚れに汚れたホイールに「K1201プラス」のハイパワースチームを当ててみよう。ここでも「真ちゅうブラシ」ををつけ、表面の汚れを溶かして浮き上がらせつつ、ブラシで軽くこすり落とす。

真ちゅうブラシ(別売りオプション)
金属のホイールに対して同じ金属の真ちゅうブラシをこすり合わせれば、相当ひっかきキズがつくのでは?と心配もあるだろうが、柔らかい材質でできていることもあり、実際キズはつきにくい。ホイールの汚れはきれいに落とすことができた。

驚くほどピカピカになった
以上、スチームクリーナーはリビングの床から窓ガラス、お風呂場、キッチン、クルマまで非常に幅広く使える。洗剤を使わないので環境に優しく、高温蒸気の除菌作用があるなど、小さな子供のいる家庭には特にありがたい。ケルヒャー社の本国・ドイツでは、家庭内で日常的にスチームクリーナーを使うシーンが見られるという。
今回紹介したケルヒャーの「K1201プラス」は実売価格3万円程度。その性能の高さと安全性や安心感、さらに豊富なオプションパーツ群を考えると、とてもコストパフォーマンスの高い製品だと言えるだろう。コメリドットコムとしても、おすすめの商品だ。