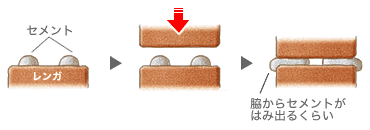レンガで作ろう「バーベキューコンロ」
※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。
はじめに・・・
レンガや枕木といったホームセンターで手に入る材料を使って本格的なバーベキューコンロ作りに挑戦してみましょう。
コメリの“レンガ師匠”と、コメリ・ドットコムHowTo取材班が実際に手がけた様子を紹介します。
用意するもの
    |
■用意する材料
|
1.下地づくり
 路盤材を敷きます |
今回は作るバーベキューコンロは、タテ1000mm×ヨコ1000mmのサイズです。コンロの周囲を1200mmの枕木で囲んで、レンガだけのコンロに格調高い質感もプラスしようという計画です。 |
|||||||||||
 スコップで大まかに広げます |
掘ったあとは下地となる部分に路盤材を敷いていきます。路盤材は「砕石」の名でも販売されています。砂利よりも石一つ一つの形が「くさび形」に近く、上からの圧力で踏み固められやすいのが特徴です。土のう袋から開けたら、スコップ等で平らにしていきましょう。 |
|||||||||||
 これが便利なコンパクターです |
さて、ここで紹介するのが『コンパクター』です。機械そのものの重圧と上下に細かく震動する接地面のおかげで、とてもスムーズに下地路盤を踏み固められます。使い方は簡単で、エンジンをかけたらあとは勝手にコンパクターが前進してくれます。カタカタカタ・・・と本体を上下に震動させながら地面を這う姿は、道路工事現場でのプロの仕事を連想させます。操る姿は文句なくカッコイイです。
|
|||||||||||
 機械を使えば簡単・キレイに仕上がります |
||||||||||||
ところで、ここでは厚みが普通の枕木の半分である「半割りサイズ」の枕木を使用しています。これは下地を深く掘る労力を軽減するためです。つまり、枕木は地面と同じ高さまで埋めたい、でも深く掘り下げるのは大変だというのがその理由です。 |
||||||||||||
2.1段目を敷く
 セメント1に対し砂は2~3 |
セメントを練るレンガを積み上げていくためのセメントを作りましょう。 (1)タフ舟などの大型容器に 砂:セメント=2~3:1 の割合で入れよく混ぜます。 |
|
 よく混ぜます |
(2)この混ぜたものをバケツに移し、水を加えてレンガゴテでよく練ります。 固さは耳たぶほどです。 |
|
 水を加えてよく練ります |
レンガの準備バーベキューコンロを作るには約400個ものレンガを使います。どんどん積み上げていくので手際よく作業するための工夫も必要です。 耐火レンガは水に濡れないようにしましょう。 濡れてしまった場合は、十分に乾燥させてから使用するようにしましょう。 |
 枕木に沿うように塗ります |
積み上げ1段目は枕木と直角に並べる練ったセメントをすくい上げて、レンガの横の長さと同じ幅ぶんだけ置いていきます。置いていくと言うよりも「塗っていく」のイメージです。 |
|
 塗ったセメントの上にレンガを設置します |
枕木に沿うように1辺を塗り終わったら、レンガをセメントの上に置きます。手でグッと上から押さえて固定したら、次のレンガをまた置いて・・・とリズミカルに進めましょう。1段目のレンガは、置いた時に周囲を囲った枕木と高さがと揃うようにするのも忘れないようにしましょう。 施工日の天候や気温にもよるが、夏などは練りセメントも塗ったそばからどんどん乾燥が進むのでスピーディーに作業することを第一に心がけましょう。 レンガは隣のレンガとのすき間(=目地)を作りながら等間隔に敷いていきます。1段目は枕木と直角に交わる方向に敷くのもポイントです。 |
|
 水平を確認しながら作業を進めます |
1辺敷き終わったら、水平器で高さが揃っているか確認しましょう。敷く事ばかりに一生懸命になって、バランスが崩れていませんか。せっかく施工したバーベキューコンロも、地面と平行になっていないのでは使いにくくてしょうがありません。 | |
 飛び出たものは叩いて高さ調整します |
飛び出ているものはハンマーの柄などでトントンと叩いて調整が必要です。 |
3.2段目以降を積み上げる
 シミュレーションで2段目以降をイメージします |
|
|||||||||||
 1段目の目地を埋めましょう |
2段目、3段目のレンガの向き
2段目のレンガは1段目と交差する状態、つまり沿う枕木と水平方向に積み上げていきます。仮に、1段目のレンガを東西方向に敷いたとすれば、2段目は南北方向に積みます。 |
|||||||||||
 積む方向に注意しましょう |
1段目の目地を埋めるそれでは2段目を積みはじめましょう。いや、その前に1段目の目地を埋めるのをお忘れなく。練ったセメントをレンガゴテを使ってレンガの目地に入れていきます。積んでしまった後では下の段の目地埋めはできないので注意しましょう。 |
|||||||||||
 3段目まで積み上げた状態です |
2段目以降を積み上げる無事、1段目の目地は埋め終わったでしょうか?そしたら1段目のレンガの上に練ったセメントを乗せます。セメントはレンガの長辺に沿って2本のレール状に乗せます。この上からレンガを置いて押さえると、中のセメントがつぶれてクッションの役割を果たし、ちょうど良い状態で固まります。
|
|||||||||||
 脇から出たセメントは半乾きにして取ります |
積み作業の進め方2段目以降のレンガ積みは、目地を埋めて、セメントを乗せて、レンガを置いて・・・の繰り返しです。ここで一つ注意したいのは下の段のセメントが「半乾き」になったのを確かめてから上の段のレンガを積むことです。セメントが乾かず柔らかい状態でどんどん積み進むと、下のセメントでレンガが滑って斜めに積んでいってしまいます。 また、作業中もセメントはどんどん乾いていくので作業をする時は「目地を埋める人」と「セメントを乗せてレンガを積む人」の2人1組で進めるのが効率的です。時々、積み上げたレンガの列が傾いていないかチェックしながら積んでいきましょう。 |
|||||||||||
 7段目まで積み上げた状態です |
|
| 次のページへ |
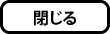


 コンパクターを使わない場合は『ガーデニングトントン』で踏み固めていきましょう。敷いた路盤材の上からトン、トン・・・と突き進みます。
コンパクターを使わない場合は『ガーデニングトントン』で踏み固めていきましょう。敷いた路盤材の上からトン、トン・・・と突き進みます。