
 ミニ盆栽を作ろう
ミニ盆栽を作ろう
動画で解説

小さな盆栽や苔玉が人気を集めています。
玄関先の和テイストの器に盛られたこんもりとした苔は、見る人をほっと優しい気持ちにさせてくれます。
今回は苔を使った「ミニ盆栽」を作りましょう。
用意するもの
・ケト土……200~300g
・赤玉土(小粒)……少々
・水ゴケ……少々
・洋風敷砂利……1個
・器(食器皿でOK)
・鉢底ネット
植え込む植物
・チゴ笹
・けやき
・ソヨゴ
・ギンゴケ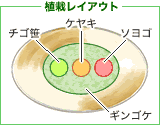
-

器は気に入った食器から選びます。深さや色合いは盆栽とのバランスを見て決めましょう。
-

植え込む山野草は、日光や水の好み具合が似ているものを合わせると管理が簡単になります。
-

ケト土は水辺の植物が土に堆積されて炭化したもの。保水力に富んでいます。
-

左はハイゴケ、右がギンゴケ。草むらから石垣、都会の道路までいたる所で入手できます。パックで売られている店もあり。
ミニ盆栽の作り方とコツ
1.土を準備する
-

ケト土に赤玉土(小粒)、水ゴケを入れ、水を加えてまぜ合わせる。水ゴケは、袋の底にたまっている粉状になったものを使う。赤玉土をまぜるのは土の通気性を保つため。
-

ケト土には植物の根なども含まれていることが多いので、この段階で取り除く。「耳たぶくらい」の固さにこねたら、丸めておく。
2.根洗いをする
-

ポットから植物を取り出し、茎をつかんで根についている土を払い落とす。
-

さらにバケツに入れた水の中で根を洗う。根洗いをするのは古い土を落として新しい土で作るため。
3.土台を作る
-

作りたい大きさよりもひと回り小さいサイズに鉢底ネットをカットする。四隅の角は丸く切っておくと上から見た際に「はみ出し」が見えにくくなる。
-

土を鉢底ネットに押さえつけながら、網の目を埋めるように付けていく。厚さは5mmほど。
メモ
鉢底ネットの上に土を盛るのはなぜ?作業台に土がくっついてしまうのを防ぐため。形ができたものを持ち上げる時に役立つだけでなく、置いた後で器を変えたくなった時も移し替えがかんたんにできる。
4.植物を植える
-

土の上に植物を置き、バランスを見ながらレイアウトを考える。今回はミニ盆栽を「島」に見立てて、3つの山野草を中央1ヶ所に寄せて植えることにした。植物を包み込むように土を盛り、全体の形を整えながら土を少しずつ足していく。
-

土の表面に苔を張る。マット状になっている苔は適当な大きさにちぎり、すき間を埋めるように「島」全体に張り付ける。乾燥したら少し水を付けて。植えた植物の根元に、小粒の炭をまく。
-

苔を崩さないようにそっと持ち上げ、皿の上に乗せる。
-

頂上に白の洋風敷砂利をちょこんと乗せて、できあがり。
バリエーション
園芸用の和鉢を使う場合
-

園芸用の和鉢は、そこに穴が空いている場合が多い。器に直接土を盛っていく場合は、鉢底ネットを穴の上に置く。
-

ケト土だけで土を盛らず、このように赤玉土やプランター培養土を使う方法もある。
苔玉を作る場合
-

いちど玉に丸めた土をつぶして広げる。
-

根の部分を包むようにして玉を作る。完全な球形でなくても、やや崩れた形や細長くつぶれた形にしても味が出る。バランスをみながら余分な土を取る。
-

苔を表面に張り付けていく。写真のように茎の長い苔は、包むような感じで苔玉にする。張り付きが悪い場合は黒のミシン糸などで巻きつけても良い。
草盆栽・苔玉ミュージアム
ミニ盆栽のお手入れ
置き場所
・ミニ盆栽に使っている植物にもよりますが、山野草は室内での管理に適さないので屋外に置いて楽しむようにします。 冬は北風が当たらない場所に移し、ビニールで覆って風よけを作ります。霜にも注意。
・その植物が生えている環境を知り、日光の当たり具合や風通しを調整します。
・室内でインテリアとして飾りたい場合は、日光不足にならないように1週間に1日程度にします。部屋の中では冷暖房の風が当たる場所や、強い光が当たるところは避けます。

メモ
室内には長く置かない。日当たりと風通しの良いところが最適。
水やり
・目の細かいジョウロか、霧吹きを使って水を与えます。
・ホースなどで勢いよく水をかけると形がくずれてしまいます。
・苔は湿り気を好むので、乾燥していないか常に気を配るようにしましょう。
・春と秋、冬は午前中に1回、 夏は朝と夕方の2回水やりをします。
・苔玉の場合は、乾燥防止に受け皿に薄く水を張っておきます。

メモ
苔が乾かないように、 つねに水やりを意識しておく。
肥料
・鉢の中の限られた土では養分が不足するので、月に2~3回液肥を与えます。
・通常よりも薄めたものを、水やりのかわりにジョウロや霧吹きで葉や根元に与えましょう。
・冬や真夏は肥料を与える必要はありません。

苔をどこで手に入れるか
ちょっと道を歩けば、苔は年じゅうどこでも手に入れることができます。探してみましょう。
-

歩道や階段
-

石垣
-

裏庭
-

ハイゴケ
-

ギンゴケ








