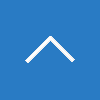農薬の基礎知識
農薬の基礎知識
動画で解説
家庭園芸薬品の分類
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 殺虫剤 | 植物に害を与える害虫を退治する薬剤。 |
| 殺ダニ剤 | 植物に寄生して害を与えるダニ類を退治する薬剤。 |
| 殺菌剤 | 植物の病気の発生を予防したり、拡大を防ぐ薬剤。 |
| 殺虫殺菌剤 | 殺虫成分と殺菌成分を混合して、害虫や病原菌を防除する薬剤。 |
| 土壌改良剤 | 植物の根の表面や内部に寄生し、加害する病原菌やセンチュウ類、 土の中にいる害虫を退治する薬剤。 |
| 誘引殺虫剤 | 害虫の好むエサに殺虫剤を混ぜて誘引し、退治する薬剤。 |
| 除草剤 | 有用植物以外で、邪魔になったり、害になる雑草を枯らす薬剤。 |
| 忌避剤 | 動物が特定の臭いや味を嫌う性質を利用して、鳥獣害を防ぐ薬剤。 |
| 殺そ剤 | 植物を有害するネズミ類の駆除薬剤。 |
| 植物生長 調整剤 |
植物の発根、矮化、開花、結実、伸長、生育などの生理機能を促進、 または抑制する薬剤。 |
| 展着剤 | 薬品を薄めて散布する時に、薬剤が害虫の体や、植物の表面によく付着するように調整液に添加する薬剤。 |
薬品の形態
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 乳剤(液体) | 水で薄めると成分が細かい粒子となり、乳濁液になる。 |
| 液剤(液体) | 水溶性の溶剤に成分を溶かしたもの。水で薄めると透明になる。 |
| 水和剤(粉末) | 水に溶けない主成分を粘土質微粉などで薄めたもので、水で薄めると微粉末が水に分散して混濁液となる。 |
| 水溶剤(粉末) | 水和剤と同じような粉末であるが、成分が水溶性なので、水で薄めると 透明な液になる。 |
| 粉剤(粉末) | 成分を粘土鉱物などと混合粉砕した微粉末。 |
| 粒剤(粒状) | 成分を鉱物土と練って粒状に固めたり、小粒石にしみ込ませたもので、成分が根や葉から吸収されるので、遅効性だが、噴霧器などがいらず、使用が簡単。 |
| エアゾール剤 | 成分を溶剤に溶かし、密封缶に噴射剤とともに充填したもので、薄める手間や噴霧器がいらないので便利。小さな庭やベランダ園芸などで使用する。 近接噴射すると冷害を起すことがあるので、注意が必要。 |
| ハンドスプレー タイプ |
成分を小型スプレー容器に充填したもので、薄める手間がいらず、容器が噴霧器になっているので便利。 近接噴射による冷害の心配もない。 |
農薬を安全に使用する
家庭園芸薬品を使用する場合、使用する人はもちろん、その植物に対しても、また周辺の植物や環境やペットに対しても、十分な配慮が必要となります。
薬剤の選び方
病害虫防除のための薬剤は、目的や用途、対象となる病害虫や植物などに応じて多種多様です。
間違った使い方をすると、充分な効果が得られなかったり、逆に植物に薬害が生じてしまうこともあります。
薬剤を選ぶポイントを把握し、正しく選んで正しく使用することが病害虫防除の基本です。
薬剤選びのポイント
- ・病害虫の種類を知り、防除目的をはっきりさせる。(虫なのか?病気なのか?を判断する。)
- ・薬剤の剤型、特性、効果等を理解して薬剤を選定する。(剤型ごとの利点、注意点を理解する。)
- ・用途や使用方法、使用面積に応じて正しく選択する。(対象作物に薬剤の適用があることを確認する。)
薬剤散布のポイント
害虫による吸汁や食害の被害の場合はもちろん、特に病気の場合は葉が変色した後に殺菌剤を散布しても、元通りにはなりません。
病害虫は、それぞれ発生の時期が異なります。
適切な防除時期を確認して散布しましょう。
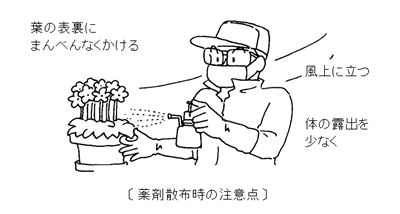
散布液の作り方
そのまま使用できる商品もありますが、乳剤・液剤・水和剤等多くの商品は水で薄めて使います。
薬剤は一度水でうすめますと保存できませんので、ラベルや説明書に記載されている使用濃度を守って作ります。
薬剤の計量、作成には「ピペット」「ハカリマーゼ」「ハカリマス」を使用すると便利です。
また、薬剤効果を高めるため、散布液を虫や葉に付きやすくする「展着剤」も混ぜ合わせて使います。
「散布用マスク」も必需品です。

表の見方
500倍の濃度の液を1L作りたい場合は乳剤・液剤では2.0mlを1Lの水に溶かす。
水和剤では2gを1Lの水に溶かす。
関連商品
病害虫の適用一覧
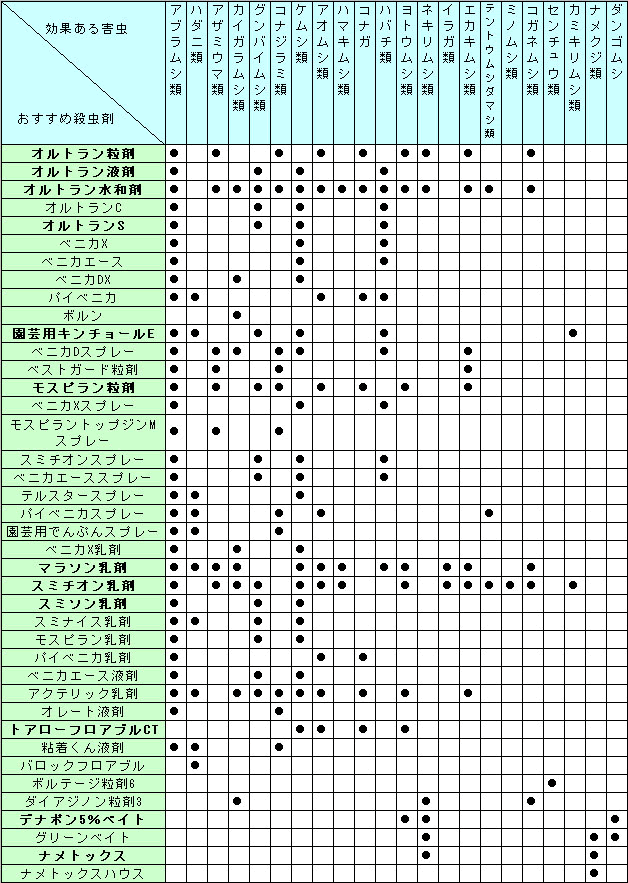
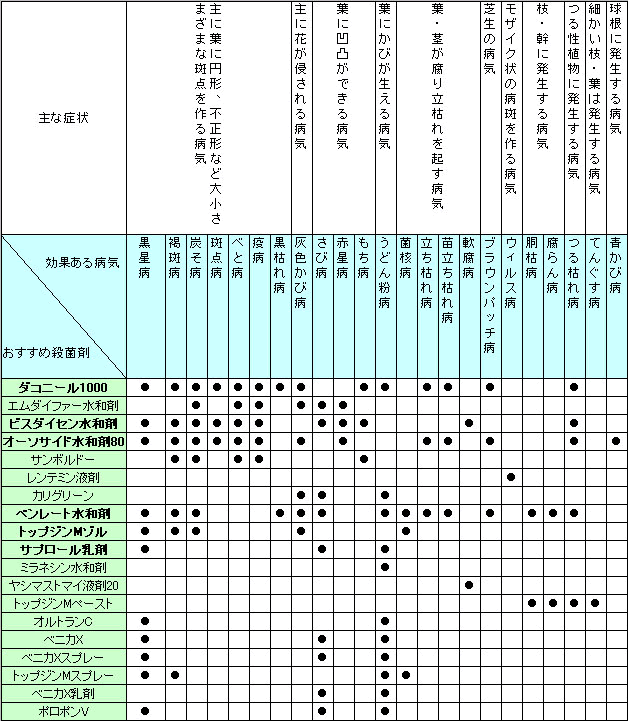
※薬剤と適用害虫は、対象植物によって異なります。
商品の適用植物をよく確認して使用してください。
薬剤の選択、及び使用の際は、必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従って使用してください。